ボルタリングが2020東京オリンピック種目に選ばれた事で、ボルタリング教室が今、とても人気を博していますが、ボルタリングをはじめロッククライミング用のシューズは一般的なシューズとは違い少し特殊です。
と言いますのも足も手同様に岩の状態を触った感触で判断し、そして指先にしっかりと力を入れて岩をつかむ必要がありますので、靴底は一般的な靴とは違いとても薄く、薄いものは靴底の厚みは3mm、厚くても5mmと非常に薄く作られています。
その為、専用靴と言っても良く、ゴツゴツとした岩場を上り下りする様なハイキングやトレッキングの様な用途には靴底が薄く向いていませんが、靴底が薄く裸足感覚で移動できる事で、不安定な足場で踏ん張った時にやはり地面を状態を感じ取る事ができると言う事は足下が安定しますので怪我が少なくなります。
そこで今回はハイキングやトレッキングと言った用途にも使えるシューズ「Sockwa X10」をご紹介致します。
アラミド繊維で作られたインソール

ではまず、このこのマリンシューズの様なクライミングシューズの様な「Sockwa X10」の最大の特徴はインソールにあります。
アウトソール(靴底)の厚みは3.5mmとクライミングシューズとしても薄い方に入りますので、土の地面の状態まで素足で地面の上に立っているかの様な肌感覚で足の裏の状態、地面の状態を感じ取れるシューズになります。
ただ靴底が薄く柔らかい分、足の動きを阻害する事なく足の動きにピッタリとシンクロし動いてくれるのですが、その分、尖った石を踏んだり、ガラス片を踏んだり、画鋲の様なものを踏んでしまうとアウトソールを突き抜け、インソールを突き抜け足にまで刺さってしまうと言う危険性があります。
そのため、この「Sockwa X10」ではインソールにアラミド繊維と呼ばれる、防弾チョッキや消防服と言った身体を保護する目的で作られている着衣に使われている非常に強度の高い繊維を使った薄さと強度の両方を合わせ持ったインソールを使っており、尖った岩を踏んだり、ガラス片を踏んだりしても足を怪我しない様に考えられています。
指を広げて踏ん張れるつま先
次にこの「Sockwa X10」は、つま先部分が最近のランニングシューズの様に指先が広がった様な形状になっているのが特徴です。
これがマリンシューズもそうですが、特にクライミングシューズ、ボルタリングシューズは岩場のほんの少し凹んだ、飛び出た部分に足を引っ掛けられる様に靴先が鳥のクチバシの様に尖った形状をしています。
ですが、つま先が尖っていると逆に歩いたり走ったりすると着地の際につま先が地面に引っ掛かりますのでクライミングシューズやボルタリングシューズはそう言う意味もあって岩場を登る以外の目的以外の仕様には向いていません。
一方この「Sockwa X10」は、歩いたり走ったりと言う事を前提にしており、つま先の踏ん張りが利くように指先が広がっておりしっかりと地面を捉える事ができる他、長距離歩いても疲れない、足が痛くならない、つま先周辺に靴擦れが出来辛いと言うメリットがあります。
丸めて持ち歩ける携帯性の良さ

そしてこの「Sockwa X10」はただアウトソールが薄く、インソールが強靱で、つま先が広がる様に作られているだけではありません。
靴そのものも全体的に薄く軽く作られており、靴下の様にとまでは行きませんが、丸めてネットやポーチに入れて持ち歩く事もできます。
ですから2ndシューズとして、ルームシューズとして、ホテルや靴を脱がなければならない場所へ行く際に携帯して行くと言った使い方もできますので、もし興味を持たれた方は下記URLをご覧ください。
https://www.kickstarter.com/projects/1577077210/sockwa-x10-feel-the-ground






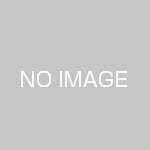




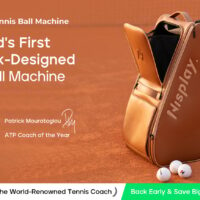




この記事へのコメントはありません。